
桐島さとし
きりしま・さとし/1979年生まれ。東京大学教養学部卒。2008年に新卒で入社した企業を退社し、豆腐作りを始める。現在は長野県伊那市の「とうふ カンパーニュ 暮らしの品 mui」にて、地元の大豆と天然にがりを使って、かまどで炊いた豆腐を販売している。
頭ばかり使って「生きていく力がない」自分に劣等感
──東大に行こうと思ったきっかけはなんですか
高校2年生の時に1年間休学して、イギリスにボランティア留学に行ったのがきっかけです。障害のある子どもたちが通う学校に住み込み、世界各国から来た他のボランティアたちと寮で共同生活をしていました。1年間ともに過ごす中で、個人間では国籍によらず友達になれても、国同士になると争いが起きることを不思議に思いました。国際関係論を学んで平和に寄与できる仕事に就きたいと思い、国際関係論を学ぶなら東大だと、進学を考え始めました。
──東大入学後も国際関係論を学びたい気持ちは変わらなかったのですか
入学してしばらくは変わらなかったのですが、2年生の時に読んだ経済学者の玉野井芳郎先生の本が、すごく面白くて……。市場経済の中では、人間や自然といった本来商品になるべきではないものまで商品になるのが問題だ、という考えに共感しました。そこから環境問題に興味を持ち、図書館でたまたま目に留まった『有機農業ハンドブック』(農山漁村文化協会)という本をきっかけに有機農業の世界にハマりました。有機農業の技術書的な側面もあるので、後になって読み返すと何がそんなに面白かったのか分からないのですが、有機農業の世界観が合っていたんでしょうね。
後期課程では、教養学部のアジア研究のコースに進学したのですが、全くアジアの研究はしませんでした。自分で自然志向の人たちや有機農業グループのイベントに参加したり、いろんな農家さんを回ったり……。卒業研究も島根県木次町で、有機農業をテーマにフィールドワークをしました。
──卒業後の進路はどのように考えていたのですか
農家さんと比べて、頭ばかり使って、生きていくための力は何もない自分に劣等感を感じていました。農家さん、職人さんへの強い憧れから就農することも考えましたが、どこかに「東大生なのに」という気持ちもあり、農業の道に進むとは決断できませんでした。一方でサラリーマンになる気もせず、4年生の7月ごろまで就職活動はしませんでした。地域で自給する持続可能なシステムを作りたいという気持ちはあったのですが、何の職業ならそれできるのか分からずにいました。
これ以上先延ばしにするとまずいと思った時、募集締め切りギリギリのタイミングで地元の長野の食品メーカーの採用試験を受けました。その企業は、社員が幸せになることが会社の目的と掲げていて、事業も年輪のように少しずつ大きくするべきだという経営方針でした。「こういう企業なら」と思い採用試験を受けたのですが、最終面接で社長に「あなたは自然人だから牧場でも経営している方が似合っている」と言われ、素直に「そうなんです。サラリーマンになるイメージが持てなくて、どうしたらいいのか分からないんです」と返したら、後日不採用通知が届きました。
「1社しか受けていないのにどうしよう」と思うと同時に、短時間で人の本質を見抜ける社長だったら、この先どうしたら良いか教えてくれるだろうと思ったんです。人事に連絡したら、なんと社長がまた時間をつくって会ってくれることになりました。人生論を話した後に、最終的には「じゃあうちの会社で勉強してみるか」と声をもらい、そう言ってくださるなら、とその会社に入社しました。

会社勤めは自分の生き方じゃなかった
──社会人4年目の時に退社し、豆腐作りを始めています
仕事は面白かったのですが、1年の時から「これは自分が生きたい生き方じゃない」と、はっきり感じていました。社内にしか目を向けずに、会社すなわち社長のために働く社員を見て、それは違うなと。社会のために働きたいと思っていました。
次女が生まれるタイミングで会社を辞めることを決め、何をやるかは辞めた後決めることにしました。当時は「半農半X」という言葉が流行っており、半分は会社員時代から始めていた農業をやり、残りの半分何か違うことをやろうと考えていました。
──なぜ豆腐作りを選んだのですか
卒業研究で木次町でフィールドワークをした際、豆腐屋さんにインタビューをしたんです。豆腐作りも見学させてもらい、出来上がった豆腐をその場で食べたのですが、衝撃でした。「こんなにおいしい豆腐を作るなんてすごい! かっこいいな」とずっと印象に残っていました。この出来事があって、会社を辞めて何をするか考えたときに、豆腐屋というのが頭に浮かんだんです。
たまたま近所に豆腐屋さんだった場所が見つかり、大豆を炊くのに使っていたかまどが残っているのを見て、面白そう!と思いました。かまどを使った昔ながらの方法の方が面白いと感じ、その場所で豆腐を作ろうと決めました。半分は直感だったのですが、もう半分は大学生の時に考えていた「地域自給のシステムづくり」が頭にありました。地元の大豆を地元の薪を使って豆腐にして、地元の人に手渡しする。顔が見える関係性をつくるというコンセプトでした。
──ゼロからの豆腐作りですが、どのように軌道に乗せたのですか
かまどで大豆を炊く製法で豆腐を作るお店がほとんどなくなっていたので、豆腐を作れるようになるのが大変でした。豆乳は作れても、天然にがりで固めるのが難しかったり、豆乳を煮る際の泡を消す「消泡剤」を使わずに作る方法が分からなかったり……。昔ながらの方法で豆腐を作っている全国の豆腐屋さんへ行き、作り方を教えてもらったり、理論的な背景である凝固反応を専門誌で学んだりして、1年かけてなんとか作れるようになり、開業しました。
開業までは家庭教師や塾講師のバイトを掛け持ちしてお金を稼いでいました。子どももいたので、どんどん貯金残高が減っていって……。でも不安より、新しいことをやりたいという希望や、わくわくの方が大きかったですね。
開業後は、話題性もあったためかお客さんが付いてくれて、比較的すぐ生活できるようになりました。

──開業後は順調にお店を続けられたのですか
全然! 開業後5年経った時に、一度お店を辞めているんです。
開業後1年半ほどで、最初に借りていたお店を出ていくことになり、新たに工場を作るのに1千万円以上借金しました。返済に充てるお金を捻出しなきゃと、作る量も増やして卸し先を拡大し、どんどん規模を大きくしたんです。それはそれで順調に滑り出したんですが、やっぱり人はというのは、評価されて大きなお金が動くようになると、魔にとらわれるところもあって……。どんどん事業を広げることを考えてしまったんですね。
かまどで炊くという外せないポイントがあったので、絶対に大量には作れない。でも拡大しようとする、という不自然なことをすると、やっぱり歪みがでてくるんですね。その時は自分がたくさん働くことでその矛盾を解決しようとして、2~3時間しか寝ずに働き続けたんです。30代で、まだ若かったしね。
お店を初めて5年目の年末、お歳暮セットを作ったりして、もうめちゃめちゃ忙しくて……。終わった頃に「もう動けない感じがする。少しの間お店を休もうかな」と思ったんです。ちょうどその時、東大の指導教員だった先生から連絡があり、卒論でフィールドワークをしていた木次町での仕事に誘われ、行くことにしました。
子どもと接する中で気付いた「自力」の限界
──木次町ではどのような経験をしたのですか
子どもたちが牧場で生活しながら学ぶ、オルタナティブスクールの運営の仕事でした。「他力塾」という名前のスクールで、先生ではなく、子どもと一緒に暮らして寄り添う「ファシリテーター」という役割をしていました。
最初のうちは自分の方が上の立場だと思い込み、子どもたちを誘導しようとしていたんです。東大出ていると、ある程度自分が優秀だと思い込んでしまう面がありますよね。でも「上」の立場の人として子どもたちを動かそうとすると、すごい反発が返ってくるんです。
そうやって子どもたちを見ていると、写し鏡のように豆腐作りを始めてから5年間の自分の姿勢が分かってきて……。他力じゃなくて、自力だったんだなと。つまり、目に見える成果を、全部自分の力で出そうと思っていたんですね。人から評価されることを求めていた時期だったとも思います。体が疲れていることにも目を向けず、自分をいつまでも働き続けられるロボットのように思っていました。自分自身だけじゃなく、一番近い家族や、友人、地域にも目が向いておらず、もっと大きなビジョンしか見ていなかったんだと思います。
どんなに成績が良かろうが、優秀だろうが、人はそれぞれ色々な形を持っていて、皆弱い部分もある。弱い部分も含めて自分を受け入れ、その上で色々なものに頼って生きるのが「他力」のあり方なのかなと、木次町で過ごす中でおぼろげながら分かってきました。2年間子どもたちと暮らして、また長野に戻り豆腐屋を再開したのですが、それからは自分の体や周りの人を大事にしようと決めました。当時と今を比較すると、自分を犠牲にする生き方がもたらすものと、自分を大切にする生き方がもたらすものの違いが分かる気がします。

取材日は近所の人と共に味噌づくりをしていた
──今はどのような気持ちで、豆腐作りに取り組んでいますか
豆腐作りを再開した後、大豆を焦がしてしまう時期があったんです。炊き方を慎重にしても焦げることが続いたのですが、最終的に薪が湿っていたのが原因と分かりました。色々やり方を工夫しても焦げていたのが、薪を変えただけですぐに焦げなくなりました。その時「今まで自分が大豆を炊いていると思っていたけど、炊いてくれているのは薪だった」と気が付いたんです。うぬぼれていたと反省すると同時に、なんて幸せな仕事だ、とも思ったんです。
薪の力、大豆の力、海水から取ったにがりの力、そういう自然の力が組み合わさっておいしい豆腐になっている。それら全ての力が上手く働くように調整するのが、自分の役割なんだと思ったんです。それ以降は「自分がなんとかおいしい豆腐を作らなくては」という姿勢から、自然にお任せすればよいという姿勢に変わり、仕事もどんどん楽しくなっていきました。
──かまどで炊く豆腐づくりの技術を次の世代に継承するため、クラウドファンディングで支援を募っていました
かまどで豆腐を作る技術を、消滅させたくないというのが第一の理由です。
46歳になり、残りの人生を数え始めると、残りの時間はすごく限られているという感覚があるんです。残された時間、自分の命を何に使うかを考えたときに、やりたいことをなんでもかんでもやる訳にはいかない。豆腐作りももちろんやりたいのですが、それだけではなく、だれかに「ほかの命」に触れる体験をしてもらうことで、その人の内側にある願いの蓋を開けてあげたいというか……。
固定観念や常識、世間体に捉われずに、自分が素直にやりたいと思うことで生きていく方が、まあまあ幸せに、生きづらさを感じることが少なく生きていけるんじゃないかなと私は思っています。そういう生き方のお手伝いがしたい気持ちもあり、クラウドファンディングを始めました。
──20代の読者に向け、メッセージをお願いします
あんまり頭で考えるより、感覚で動いた方が面白いよ、と伝えたいです。私も頭でっかちな部分があったのですが、それでも会社を辞める時に、かまどが残る豆腐屋さんの跡地を見て「やりたい!」と感じ、その思いに素直に従えたんです。感性は大事だなと思います。
短期的に失敗という結果が出ることはあるかもしれませんが、何事も「間違い」というのはないと思います。なので、失敗してみればいいし「駄目なことは一つもないので、何でもいいんじゃない」というのがメッセージでしょうか。
【関連記事】
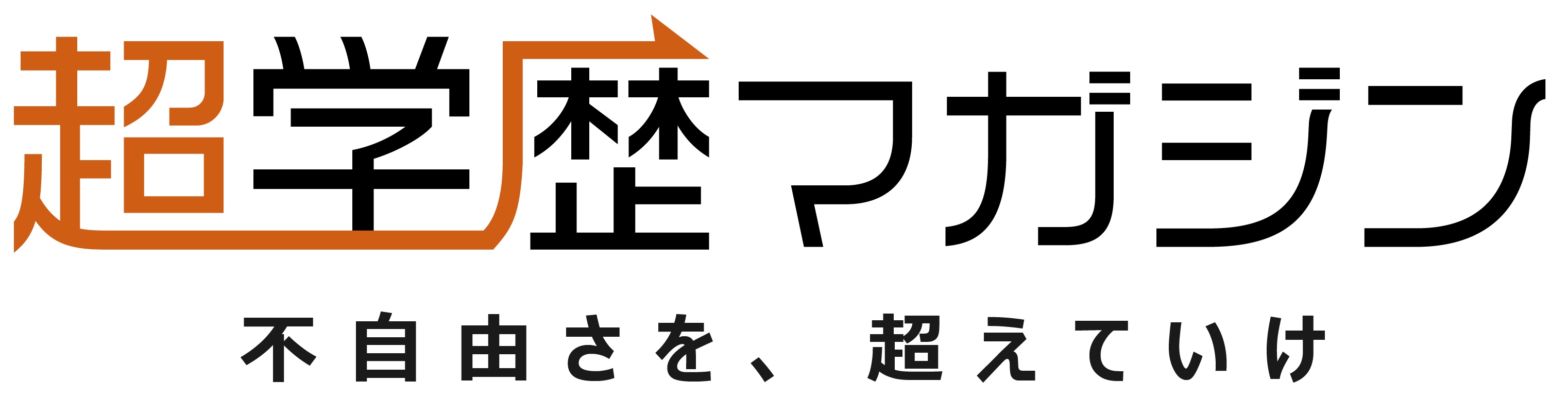

COMMENTS